【犬のパテラ】手術は必要?費用と自宅でできる予防ケア
「愛犬がスキップみたいな変な歩き方をする…」「病院でパテラと診断されたけど、手術は必須なの?」
愛犬の足にいつもと違う様子が見られると、胸が締め付けられるように心配になりますよね。特にトイ・プードルやチワワといった小型犬と暮らす飼い主さんにとって、「膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)」、通称「パテラ」は、決して他人事ではない病気です。我が家の愛犬(トイプードル)が獣医師さんから「パテラの気があるね」と告げられた時、一瞬、頭が真っ白になったことを今でも覚えています。
でも、過度に心配しすぎる必要はありません。パテラは正しい知識を持って早期に対策すれば、上手に付き合っていける病気です。この記事では、愛犬の足に不安を抱える飼い主さんのために、以下の内容を分かりやすく解説します。
- パテラの基礎知識と原因
- 症状の重さを示すグレードの見分け方
- 手術の必要性や費用、治療法の選択肢
- 今日から自宅で始められる具体的な予防・悪化防止策
この記事を読めば、パテラに対する漠然とした不安が解消され、愛犬のために今すぐ何をすべきかが明確になります。大切な愛犬の足を守るため、一緒に知識を深めていきましょう。
そもそも犬の「パテラ(膝蓋骨脱臼)」ってどんな病気?
まず、パテラがどのような状態なのかを、専門用語を使いつつも簡単に解説しますね。人間の膝にも「お皿」がありますよね。犬にも同じように「膝蓋骨(しつがいこつ)」というお皿状の骨があります。この膝蓋骨は、普段、太ももの骨(大腿骨)にある「滑車溝(かっしゃこう)」という“溝のレール”の上をスムーズに動くことで、膝の曲げ伸ばしをサポートしています。
ところが、何らかの原因でこの膝蓋骨が本来あるべき“レール”から内側、または外側に外れてしまうことがあります。この状態が「膝蓋骨脱臼(パテラ)」です。ほとんどの場合は内側に外れる「内方脱臼」で、特に小型犬に多く見られます。
パテラの原因は?うちの飼い方が悪かったの?
「うちの子がパテラになったのは、私の飼い方が原因かも…」とご自身を責めてしまう飼い主さんもいらっしゃいますが、その必要はありません。パテラの原因の多くは、生まれつきの体質によるものです。
主な原因は「先天性」!遺伝的な要因が大きい
パテラを発症するワンちゃんの多くは、遺伝的に膝関節まわりの骨や筋肉の形に特徴があります。
- 滑車溝(レール)が浅い:膝蓋骨がはまるべきレールの溝が生まれつき浅いため、少しの衝撃で外れやすくなっています。
- 骨の形や靭帯の異常:太ももやスネの骨が少し変形していたり、膝蓋骨を支える靭帯の位置がずれていたりすることで、膝蓋骨が引っ張られて脱臼しやすくなります。
これらの要因は遺伝による影響が大きいため、残念ながら飼い方だけで完全に予防することは難しいのが現実です。
特にパテラになりやすい犬種
以下の犬種は、遺伝的にパテラになりやすいと言われています。
- トイ・プードル
- チワワ
- ポメラニアン
- ヨークシャー・テリア
- マルチーズ
- シーズー など
もちろん、ここに挙げた犬種以外やミックス犬でも発症する可能性は十分にあります。
後天的な要因で発症・悪化することも
生まれつきの素因に加えて、以下のような後天的な要因が引き金になったり、症状を悪化させたりすることがあります。ここは飼い主さんの工夫で対策できる部分です!
- 膝への強い衝撃:ソファからの飛び降り、転倒、交通事故など。
- 肥満による体重負荷:体重が増えるほど、歩くだけで膝関節に大きな負担がかかり続けます。
- 滑りやすい床:フローリングなどのツルツルした床は、犬が常に踏ん張る必要があり、脱臼を誘発する大きな原因になります。
【症状別】愛犬のパテラ重症度セルフチェックリスト
パテラは症状の重さによって「グレード1」から「グレード4」の4段階に分けられます。愛犬に以下のようなサインが見られたら、どのグレードに当てはまりそうか確認してみましょう。あくまで目安として、正確な診断は必ず動物病院で受けてくださいね。
見逃さないで!パテラの初期サイン
- 歩いている時、後ろ足をぴょこっと上げてスキップのような歩き方をする
- 歩き方がおかしい(びっこを引く、腰を落として歩く)
- 抱き上げた時や足を触った時に「キャン!」と鳴いて痛がる
- 大好きだった散歩や運動を嫌がるようになった
- ソファや階段の上り下りをためらうようになった
症状の重さを示す4つのグレード
【グレード1】
普段は正常な位置にありますが、指で押すと脱臼します。しかし、指を離せば自然に元の位置に戻ります。無症状のことが多いですが、たまにスキップするようなしぐさが見られます。
【グレード2】
膝を曲げ伸ばしする際に、時々脱臼するようになります。脱臼した瞬間に「キャン!」と鳴いたり、足を気にしたりしますが、自分で足を動かして元に戻すことができます。この段階から関節炎を併発しやすくなります。
【グレード3】
膝蓋骨が常に脱臼した状態になります。指で押せば一時的に元に戻せますが、すぐにまた外れてしまいます。腰をかがめて歩いたり、がに股になったりと、常に歩行の異常が見られるようになります。
【グレード4】
膝蓋骨は常に脱臼しており、指で押しても元の位置に戻すことができません。骨の変形も重度になっていることが多く、足を曲げたままだったり、うずくまるようにしか歩けなかったりします。
パテラの治療法|手術は必要?費用はどれくらい?
「パテラと診断されたら、すぐ手術しないといけないの?」と不安になりますよね。治療法はグレードや症状によって異なり、大きく「保存療法」と「外科的治療(手術)」に分けられます。
【グレード1〜2向け】手術しない「保存療法」とは
グレード1や、グレード2でも症状が軽く、日常生活に支障がない場合は、手術をせずに様子を見ることが多いです。これを「保存療法」といいます。
- 体重管理:肥満は膝の最大の敵です。適正体重の維持が最も重要になります。
- 運動制限:ジャンプや急なダッシュ、階段の上り下りなど、膝に負担のかかる激しい運動は避けましょう。
- 投薬:痛みや炎症が強い場合には、獣医師から痛み止め(消炎鎮痛剤)が処方されます。
- サプリメントの活用:関節の健康維持をサポートする「グルコサミン」や「コンドロイチン」などが配合されたサプリメントも有効です。最近では、おやつ感覚で喜んで食べてくれるチュアブルタイプも人気です。毎日のごはんにプラスして、手軽に関節ケアを始めてみるのも良いでしょう。
【グレード2〜4向け】痛みを解放する「外科手術」
グレード2以上で脱臼を頻繁に繰り返し痛みを伴う場合や、グレード3、4では手術が推奨されます。手術と聞くと怖く感じるかもしれませんが、愛犬を痛みから解放し、将来の関節炎や前十字靭帯断裂といった、より重い病気のリスクを減らすための前向きな治療法です。
主な手術には、膝蓋骨がはまる溝を深くする「滑車溝造溝術」や、骨の一部を調整して靭帯の位置を正常に戻す「脛骨粗面転移術」などがあり、症状に合わせて複数の術式が組み合わされます。
気になる手術費用は、犬の大きさや症状、病院によって20万円〜50万円程度が目安となります。こうした高額な治療費は大きな負担ですよね。万が一の時に備え、治療費の補償が受けられるペット保険を検討しておくのも一つの賢い選択です。様々なプランがあるので、一度比較サイトなどでご家庭に合った保険を探してみてはいかがでしょうか。
今日からできる!パテラ予防と悪化を防ぐ日常ケア3選
先天性の要因が大きいパテラですが、日常生活の工夫で発症や悪化のリスクを大きく減らすことが可能です。愛犬の足を守るために、今日からできる3つのケアを始めましょう!
① 最重要!食事管理で適正体重をキープ
繰り返しになりますが、体重管理はパテラ対策の基本中の基本です。体重が1kg増えるだけで、膝にはその何倍もの負担がかかります。日々の食事管理を徹底し、愛犬の体を触って肋骨が感じられるくらいの体型を維持しましょう。
最近では、低カロリーでも満腹感が得られる体重管理用のドッグフードや、関節ケア成分が配合されたフードも豊富にあります。愛犬の食いつきや体質に合ったものを選んであげてくださいね。
② 滑って転倒は絶対NG!安全な住環境づくり
ツルツルと滑るフローリングは、犬の膝にとって非常に危険です。常に足を踏ん張るため、関節に大きな負担がかかり、脱臼のリスクを高めます。我が家でも、愛犬が走り回るリビングには滑り止めマットを敷いています。
- 床材の見直し:カーペットやコルクマット、滑り止め効果のあるペット用マットを敷きましょう。愛犬がよく通る場所に部分的に敷くだけでも効果絶大です。
- 爪と足裏の毛のケア:爪が伸びていたり、足裏の毛が肉球にかかっていたりすると、ブレーキが効かず滑りやすくなります。こまめなカットを心がけましょう。
- 段差の解消:ソファやベッドへの上り下りは、膝に大きな衝撃を与えます。ペット用のスロープやステップを設置し、飛び降りを防いであげましょう。
③ 筋力は落とさない!関節に優しい運動
膝関節を安定させるためには、周りの筋肉を維持することが大切です。ただし、やり過ぎは禁物。急な方向転換やジャンプ、ボール投げなどの激しい運動は避け、ゆっくりとしたペースでの散歩で、継続的に筋力を維持することを心がけましょう。関節に負担をかけずに筋力アップできる水中トレーニング(ハイドロセラピー)なども、選択肢の一つです。
まとめ:愛犬のサインを見逃さず、まずは獣医師に相談を
犬の膝蓋骨脱臼(パテラ)は、特に小型犬にとっては身近な病気です。しかし、むやみに怖がる必要はありません。大切なのは、日頃から愛犬の歩き方や様子をよく観察し、「あれ?」という小さな変化にいち早く気づいてあげることです。
もし少しでも気になるサインが見られたら、自己判断せずに、まずはかかりつけの動物病院で獣医師に相談してください。早期に適切な診断を受けることが、愛犬の足の健康を守るための何よりの第一歩となります。
体重管理や生活環境の整備など、飼い主さんにできることはたくさんあります。この記事で得た知識を活かして、今日からできるケアを実践してみてください。あなたと愛犬の毎日が、より健やかで快適なものになることを心から願っています。



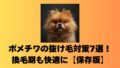
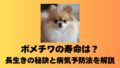
コメント