マルプーの病気予防ガイド!長生きのための飼い方とは
ふわふわの被毛に愛くるしい瞳。マルチーズとトイプードルの魅力を受け継いだミックス犬「マルプー」との生活は、何物にも代えがたい幸せな時間ですよね。
しかし、その一方で「うちの子がなりやすい病気って何だろう?」「どうすれば、一日でも長く健康でいてくれるかな?」といった不安を抱えている飼い主さんも多いのではないでしょうか。
実は、マルプーはその可愛らしい見た目や体の小ささゆえに、特有のかかりやすい病気がいくつか存在します。
そこで、この記事では、マルプーが特になりやすい代表的な病気と、今日からすぐに実践できる具体的な予防法について、初めて犬を飼う方にも分かりやすく徹底解説します。正しい知識を身につけて、大切な愛犬との毎日をもっと豊かで幸せなものにしていきましょう。
要注意!マルプーが特になりやすい病気5選
まずは、マルプーがどのような病気にかかりやすいのかを知ることから始めましょう。早期発見が何よりも重要ですので、日々のチェックの参考にしてください。
1. 膝蓋骨脱臼(パテラ)
はじめに、マルプーのような小型犬に最も多く見られる遺伝的な疾患が「膝蓋骨脱臼(しつがいこつだっきゅう)」、通称「パテラ」です。これは、後ろ足の膝にあるお皿(膝蓋骨)が、正常な位置からずれてしまう病気です。
その原因は、遺伝的な要因が大きいとされていますが、それだけでなく、フローリングなどの滑りやすい床での生活、ソファからの飛び降り、あるいは肥満などが引き金になることも少なくありません。したがって、日常生活の環境が大きく影響するのです。
症状としては、歩いている時に急に後ろ足を一本上げてケンケンしたり、スキップのような不自然な歩き方をしたりします。初期段階では痛みを伴わないことも多く、飼い主さんが気づきにくい場合もありますが、放置して重症化すると、関節炎を引き起こしたり、歩行が困難になったりすることもあります。そのため、日頃から歩き方を注意深く観察することが大切です。
2. 涙やけ
次に、マルプーの愛らしい顔に赤茶色の跡を作ってしまう「涙やけ」も、多くの飼い主さんが抱える悩みのひとつです。これは、涙が常に目の周りに溢れていることで、その成分によって毛が変色し、細菌が繁殖してしまう状態を指します。
涙やけが起こる原因は様々です。例えば、涙を排出する鼻涙管(びるいかん)が詰まっていたり、逆さまつげが眼球を刺激していたりする構造的な問題が考えられます。あるいは、ドッグフードが体に合わずアレルギー反応を起こしていることや、単純に目の周りのケア不足が原因の場合もあります。
見た目の問題だけでなく、濡れた状態が続くと皮膚炎を引き起こす可能性もあるため、こまめに涙を拭き取り、目の周りを清潔に保つことが非常に重要です。
3. 皮膚疾患(アレルギー性皮膚炎など)
マルプーの魅力である豊かでカールした被毛は、その一方で、皮膚トラブルの原因にもなり得ます。なぜなら、毛が密集しているため通気性が悪くなり、湿気がこもりやすいからです。
その結果、細菌や真菌が繁殖しやすく、アレルギー性皮膚炎や湿疹、膿皮症(のうひしょう)といった皮膚疾患を発症しやすくなります。特に、食べ物や花粉、ハウスダストなどが原因でアレルギーを起こす子も少なくありません。
体を頻繁に掻いたり、同じ場所を舐め続けたり、皮膚に赤みやフケが見られたりしたら、それは皮膚トラブルのサインかもしれません。これを防ぐためには、定期的なブラッシングで毛のもつれを防ぎ、皮膚の通気性を保つことが何よりも効果的です。
4. 歯周病
歯周病は、3歳以上の犬の約8割が罹患していると言われるほど一般的な病気ですが、マルプーは特に注意が必要です。というのも、マルプーは顎が小さく、歯と歯の間隔が狭いため、食べかすが非常に詰まりやすいのです。
そして、その食べかすを栄養源として歯垢(プラーク)が増殖し、やがて硬い歯石となって歯茎に炎症を引き起こします。これが歯周病です。悪化すると、強い口臭、歯茎からの出血、さらには歯が抜け落ちてしまうこともあります。また、歯周病菌が血管を通って全身に回り、心臓病や腎臓病といった深刻な病気を引き起こす可能性も指摘されています。
ですから、「たかが口の中の病気」と侮らず、毎日の歯磨きを習慣づけることが、全身の健康を守ることに繋がるのです。
5. 気管虚脱(きかんきょだつ)
最後に、「気管虚脱」も小型犬に多い病気です。これは、呼吸の通り道である気管が、本来の筒状を保てずに途中で潰れてしまい、呼吸がしづらくなる病気を指します。
主な症状は、興奮した時や水を飲んだ後などに「ガーガー」「ゼーゼー」といったアヒルの鳴き声のような乾いた咳をすることです。遺伝的な要因もありますが、肥満や過度な興奮、そして首輪で強く引っ張ることなどが症状を悪化させる原因となります。
重症化すると呼吸困難に陥ることもあるため、愛犬の咳が気になったら、早めに獣医師に相談しましょう。また、普段から首に負担のかからないハーネス(胴輪)を使用することも、有効な予防策の一つです。
今日からできる!愛犬を病気から守る5つの予防法
さて、ここまでマルプーがなりやすい病気について解説してきましたが、過度に心配する必要はありません。なぜなら、これらの病気の多くは、飼い主さんの日々の心がけで十分に予防・軽減できるからです。ここでは、今日からすぐに実践できる5つの予防法をご紹介します。
1. 適切な食事管理と体重コントロール
まず基本となるのが、栄養バランスの取れた食事です。マルプーの健康を維持するためには、高品質なタンパク質を含んだ総合栄養食を選びましょう。アレルギーが疑われる場合は、獣医師に相談の上、アレルギー対応のフードを試すのも良い方法です。
そして、食事管理において最も重要なのが「適切な体重の維持」です。肥満は、膝蓋骨脱臼や気管虚脱、心臓病など、あらゆる病気のリスクを高める「万病のもと」です。したがって、パッケージに記載された給与量を守り、おやつの与えすぎにはくれぐれも注意してください。愛犬が可愛いからといって、人間の食べ物を与えるのは絶対にやめましょう。
2. 適度な運動と日々のボディケア
マルプーは小型犬ですが、トイプードルの血を引いているため、比較的活発で遊び好きです。そのため、毎日の散歩や室内での遊びを通して、適度な運動をさせてあげることが、ストレス発散と肥満防止に繋がります。
ただし、過度な運動や高い場所からのジャンプは、逆に関節を痛める原因になります。あくまで、愛犬のペースに合わせた無理のない運動を心がけましょう。
さらに、皮膚疾患や歯周病を防ぐためには、毎日のケアが欠かせません。具体的には、毛のもつれを防ぐブラッシング、口内を清潔に保つ歯磨き、そして涙やけを防ぐために目の周りを優しく拭くことなどを習慣にしましょう。こうしたスキンシップは、病気の早期発見にも繋がります。
3. 安全で快適な室内環境の整備
マルプーが多くの時間を過ごす室内環境を整えることも、病気の予防において非常に重要です。
特に、膝蓋骨脱臼を予防するためには、滑りにくい床材を選ぶことが効果的です。フローリングの場合は、カーペットやマットを敷くだけでも、足腰への負担を大幅に軽減できます。また、ソファやベッドにはペット用のスロープを設置し、ジャンプによる衝撃を避ける工夫をしましょう。
加えて、皮膚や気管がデリケートなマルプーのために、室内の温度と湿度を適切に管理することも大切です。快適な環境は、ストレスの軽減にも繋がります。
4. 定期的な健康診断と予防接種
言葉を話せない愛犬の健康を守るためには、動物病院での定期的な健康診断が不可欠です。症状が出ていなくても、年に1〜2回は健康診断を受け、病気の早期発見・早期治療に努めましょう。これにより、飼い主さんが気づきにくい病気のサインを見つけられる可能性が高まります。
また、混合ワクチンの接種や、ノミ・ダニ、フィラリアといった寄生虫の予防も、感染症から愛犬を守るための基本です。獣医師の指示に従い、忘れずに行いましょう。
5. ストレスを溜めさせない工夫
マルプーは甘えん坊で寂しがり屋な一面も持っています。そのため、長時間の留守番やコミュニケーション不足は、大きなストレスとなり、問題行動や体調不良の原因になることがあります。
ですから、できるだけ一緒に過ごす時間を確保し、優しく声をかけたり、おもちゃで遊んであげたりすることが大切です。留守番をさせる際には、愛犬が安心して過ごせる静かなスペースを用意し、知育トイなどを与えて退屈させない工夫をするのも良いでしょう。飼い主さんとの信頼関係が、マルプーの心と体の健康を支えるのです。
まとめ:正しい知識でマルプーとの幸せな毎日を
今回は、マルプーがなりやすい病気と、その具体的な予防法について詳しく解説しました。
- なりやすい病気:膝蓋骨脱臼、涙やけ、皮膚疾患、歯周病、気管虚脱
- 重要な予防法:食事・体重管理、適度な運動と日々のケア、安全な室内環境、定期健診、ストレス軽減
病気の話をすると、つい不安な気持ちになってしまうかもしれません。しかし、最も大切なのは、飼い主さんが正しい知識を持ち、日々の生活の中で愛情を持って愛犬の小さな変化に気づいてあげることです。
今回ご紹介したポイントを参考に、日々のケアを丁寧に行うことが、何よりの病気予防になります。大切な家族であるマルプーと、一日でも長く、かけがえのない幸せな時間を過ごしてくださいね。
★病気予防同様マルプーとの相性も大切>>>![]()

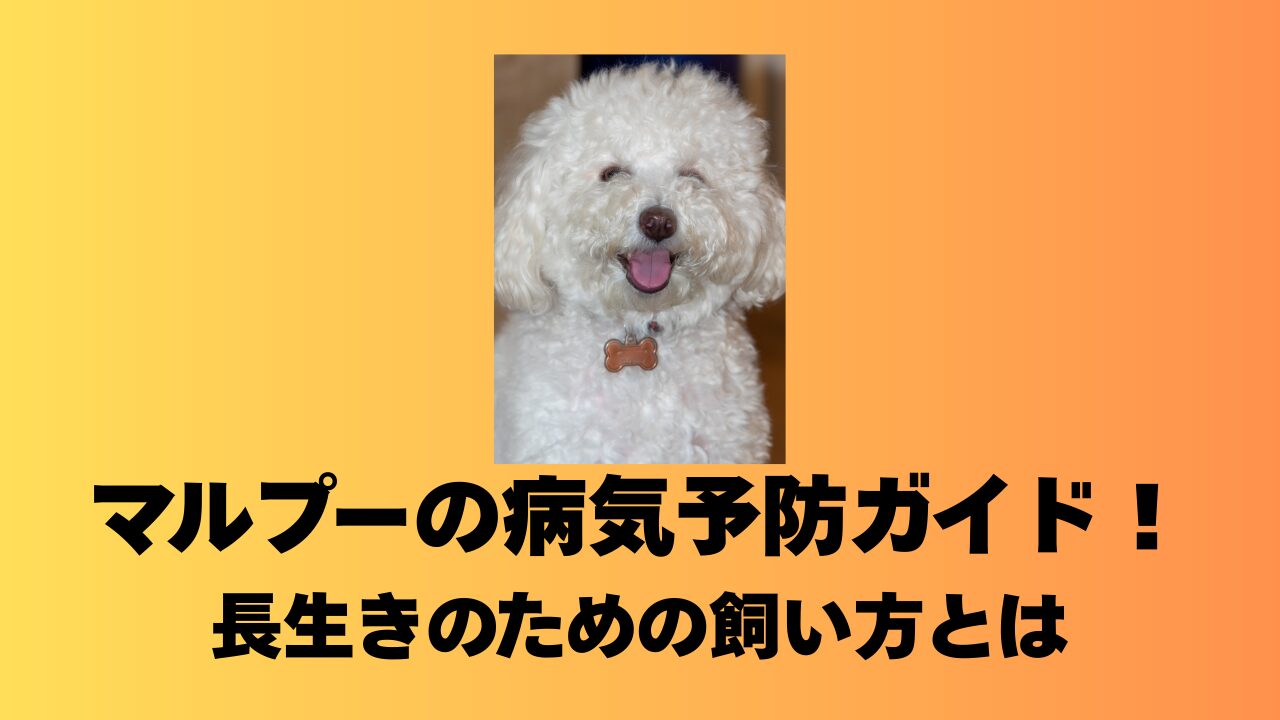




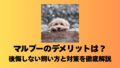

コメント